(最終回)
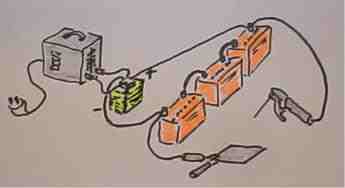
現物は譲渡してしまっているのでイラスト混じりで。
2003.10.26

〔家庭用?溶接機のパワーアップ〕
(最終回)
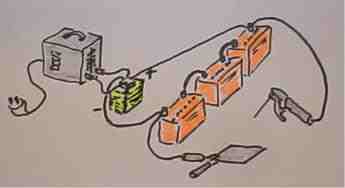
現物は譲渡してしまっているのでイラスト混じりで。
2003.10.26

家庭用?溶接機システムで現在所有している物は、この放熱器付きのブリッジ整流器だけになってしまっています。そこで申し訳ありませんが「イラスト」でご勘弁下さい。
バッテリーは軽自動車用の40Aの物で十分です。カーショップで特価品なら1個4千円ぐらいで購入出来ます。最低3個は必要です。それから「ターミナル」も2組以上必要です。この手のバッテリーのターミナルはかなり小さいので購入時注意してください。
ブリッジ整流器は、「耐圧400V・100A」ぐらい必要です。千円ぐらいでしょうか、放熱板は最低でも「2ミリのアルミ板」10センチ×10センチ以上が望ましいです。
溶接機本体は普段は充電適正電圧にする為のタダのトランスとして使用します。整流器までの電線と、バッテリーまでの電線は1.6ミリのFケーブルで十分です。充電時「2A」ぐらいしか流れませんし、溶接時でも「30V
30ー40A」程度ですので「ビニール平行線」でも良いくらいです。(溶接が短時間の場合)
全体の流れのくどい説明。
くどいようですが最初からご説明します。家庭用のコンセントからは「100V 15A」で 1500Wまでしか(実際はもう少し)とれません、トランスで 40Vまで下げても、1500/40 で 37.5Aがいいところです。(効率無視)家にきている大元のブレーカーから直にとらなければ二次電流 40A以上なんて絶対流せないのは明白です。溶接のたびにブレーカーに結線するのは面倒です。そこでたりない分を「バッテリーで補ってもらおう」・・・と言うわけです。
問題はどの程度補うか?、です。
コンセントからの入力で、二次電流40Aは確実にとれます。ところで最初のお約束、「玄関先でバリバリ」ですが、私の考えでは二次側 「40V 80A」 が最低「バリバリ」です。というわけで「軽自動車用40Aバッテリー 3個か4個」と言うわけです。(この大きさなら安いので新品購入でも後悔しません、私の元同僚もいまだに現場用として使っています。2.6ミリ・3.2ミリの溶接棒連続4本はいきます。ま、補修用程度ですけどホビー的には十分)
安全面、みたいな。(装置としての)
充電電圧等がいい加減ですが、自動車用バッテリーは丈夫なので結果オーライです。40Vの電圧でなんでバッテリー4個の48Vが充電出来るんだー ですが、出来るんです。ルート2です。やってみればわかります。
「アークの発生 = ショート 」、と思うでしょうが違います。

直流50Vレンジです。アークを発生している最中の電圧です。32V ぐらいを表示しています。(バッテリー4個で実験中)溶接棒が取られた状態で(ひっついて マジ ショートの時)約「13V」でした、ところでバッテリー式溶接でこうなると急激に容量が無くなります。私の経験では8秒ぐらいで空っぽになります。その前に溶接棒全体が灼熱して溶ければいいんですが、(よくないっ、すぐ離すべき)ちょっとパワーが落ちているときに「2.6ミリ」以上の溶接棒だったりすると1時間以上充電しないと回復しなかったりします。
あっそうそう、そういうわけで「ブリッジ整流器」は破損しませんが、出来るだけでかい物にしてください。
余計なウンチク。
ホルダー側を+につないだ時と−につないだ時とは母材の熔解深さが変わるそうです。深く鋭く溶けたり表面に浅く広がったりするそうです。(専門書より)私には良くわかりません、(っていうか断面見たこと無い)それから溶接音?ですが、
交流溶接 ・・・ バリバリバリバリーーー
直流溶接 ・・・ シヤァァァーーー
TIG溶接 ・・・ ポーーー
てな、音がします。
「スポット溶接機」ですが、「二次側電圧 1ー1.5V 二次側電流 5000A以上」必要です。家庭用コンセントからでは全く使えませんし、バッテリーも使えません、将来サイリスタかなんかで低電圧超大電流の物が発明されれば別ですが、(それに溶接したところのすぐそばは溶着部分がバイパスになって溶接出来ないのです)自作出来ますが労力の割には使えません。(と、私は思う、活躍するのは自動車組み立て工場だけ?あと大量生産工場、私・持ってるけど全く使う気にならない、無いと困るけど)
溶接ネタ終わります。あとは何か作るときに・・・。
2003.10.26
2003.10.23
〔家庭用?溶接機のパワーアップ〕


今回の主役。
パワーアップというより別物みたいになります。
2003.10.23
家庭用?溶接機として売られているセットをバリバリにパワーアップします。その前に〔使用率〕という物について能書きを述べさしてください、多少の間違いありましたらご指摘下さい、訂正させていただきます。 メール
交流抵抗アーク溶接機の使用率
この手の溶接機には〔使用率〕という物があります。簡単にいいますと「連続してどのぐらいの時間使えるか」と、いう奴ですね、本体のどこかに必ず表示されています。たとえば 10% と表示されていたとすると、「6秒間溶接したら、直ちに54秒間休みなさい !! 」と、いうわけです。(大体、実際にはもっと使えますけど)ずいぶん少ないようですが、実際の作業には「溶接棒の交換作業」とか「部材のセット」とか溶接していない時間が結構ありますから普通はあまり気にしなくても良いと思います。
では何故休ませないといけないかといいますと、トランスが発熱してしまうからです。鉄心の温度が上がると電磁誘導の効率が悪くなって、いつの間にかアークがショボショボになります。その時はもう遅くトランスは煙を出してます。火の手が上がることもあります。私も過去に1台パーにしたことがあります。工業用200Vの溶接機でも使用率は40%ぐらいです。ま、1メートルも2メートルも連続して溶接するような事をしなければ問題ありません。
バッテリー式直流アーク溶接機の使用率
バッテリー式の場合の使用率は前述のとは全然違う意味合いになります。自動車のバッテリーの役目は色々ありますが、一番電力を必要とするのはエンジンをかける時のスターターモーターです。スターターモーターにはかなり太い電線が使われています。ところでこのバッテリーを溶接に使うときは、大体ですがスターターモーターの3倍以上流れていると思われます。(あくまで私のカンです。相対的にそんな気がします)
エンジンの調子が悪いとなかなかかからない場合があります。そのうち 「ウィン ウィン」 とかいって完全にかかりそうもなくなった経験はありませんか?、あの時間の3分の1の時間で溶接時間(電力の蓄え)は終わりになります。すると充電しなければなりません、これがバッテリー式の使用率になります。市販の「バッテリー式溶接機」でなんと
5% ぐらいです。大型車の150Aバッテリー 4個使用でも 10% いきません。(つまりそれだけ激しく使う、ほとんどショートだもんね)
たとえて言うと「バッテリー式溶接機」は定期預金みたいな物です。コツコツと貯めて「ある時期 パァーッ 」と使うわけです。貯めている時間が短いと「使うときもそれなりショボショボ」になります。(現場経験)つまりバッテリー式溶接の使用率は、充電時間対使用時間の比率になります。(エンジンウェルダーは 100% かしら?)

これはご存じ、家庭用のコンセントです。(我が家です。って言うより私が工事しました。)
これは通称 100V15A とれるコンセントです。ところで2口ありますが両方から15Aとれます。ところがこれが大事なんですが「同時」にはとれません、壁の中の電線に容量が無いのです。(大部分)ですからここから取り出せる電力は合わせて 1.5Kw までです。(もう少しとれますけど)
さて、ここからが本番
つまり「家庭用溶接機」の電源をコンセントから取ってはダメなんです。1500W程度しかとれませんから、(ホットプレートでお好み焼き程度)それならどうすれば良いかといいますと、「配電盤の大元ブレーカー」から直に取ればよいのです。これで「家庭用溶接機」のちゃんとした(メーカーがはっきり言っていない)使い方がわかりました。(おいおい)
それはそれで試してください、家庭用?溶接機として売られているセットは前にも書きましたが「ワゴンセール」で1万円以下で時々売られています。セットですから本体のほかに「溶接面」「ホルダー」「アースクリップ」その他溶接棒までついている場合があります。ちょっと華奢ですがホビー的には最高です。この本体のトランスを溶接用としてではなく「充電用トランス」と考えたらいかがでしょうか、二次電圧は大抵 40V 前後です。とすると二次電流は 30A そこそこ(家庭用コンセントから取った場合)です。これをバッテリーの充電電流にします。(大丈夫です。バッテリーに 30A で充電・・・なんてことにはなりませんから)
そこで表記の「ブリッジ整流器」の登場です。本体の二次出力を直にブリッジ整流器に接続します。そして取り出される直流をバッテリーの充電電流にします。バッテリーはカーショップ等で「軽自動車用の
40A」のものを3個か4個購入して(新品でも4千円ぐらいです)使います。(昔私は職人として使っていました)新品を買っても損は無いと思います。
ところでここで問題です。前に中古のバッテリーで80A・・・とか書いていたのに何故ここで容量が小さくなって
40A のバッテリーか? と、言いますと、
家庭用溶接機の本体トランスを充電用のトランスとして使います
各バッテリーはそれにより常にフル充電状態になります
アーク発生の時(溶接の時)、バッテリーは持てる力全て( 40A )を放出します。その時充電回路は一緒に持てる力全て(つまり 30A )も出します。結果、相乗効果により溶接電流は 70A になります。それからそれからこれはオマケなんですが、アーク(放電)が終わると直ちに充電が始まります。(これが良いところ)
つまりこれが「家庭用?溶接機」のパワーアップ法、と言うわけです。(助っ人を頼むのだ !! )色々疑問があると思います。その辺は次回に。
ショート状態なのに何故「ブリッジ整流器」は破損しないか・・・
バッテリーがつながっています。

二次側電流計です。直流10Aです。充電電流監視用ですが、アーク発生時には放電電流測定になります。メーター振り切っていますが(アーク発生中)、感じ 30A ぐらいです。(針の動きで・もっとだったら針曲がってるっ)

この時電圧は 30V ほどです。(アーク発生中)つまりショートはしていません、 だから「ブリッジ整流器」は無事です
次回に続きます。
2003.10.23
戻る